メインメニュー
大津絵には江戸後期に絵種を十種に絞り、もっぱら護符として売られた時代がありました。文化・文政の頃から徐々に大津絵の主となり、幕末には他の図柄はほとんど描かれなくなってしまったようです。
人気は依然高かったものの、初期の風格を失い、美術価値が低いとされることも多い時期です。
この頃、定められた大津絵十種とは以下のものです。
|
画題
|
効用
|
|
長命を保ち百事如意
|
|
|
雷除け
|
|
|
利益を収め失物手に入る
|
|
|
愛嬌加わり良縁を得る
|
|
|
倒れぬ符
|
|
|
小児の夜泣きを止め悪魔を払う
|
|
| 諸事円満に解決し水魚の交わりを結ぶ | |
|
一路平安道中安全
|
|
|
身体剛健にして大金を持つ
|
|
|
目的貫徹思い事叶う
|
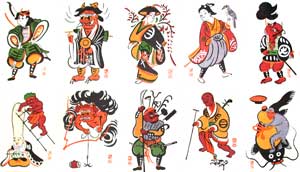
これら十種の大津絵をモチーフに作られたのが「大津絵節」であり、大津宿柴屋町の遊女が歌い始めたものとも言われますが、定かではありません。
大津絵節は大津から京、上方、江戸、そして全国へと伝播していきました。
各地で人気を博した大津絵節ですが、旋律・歌詞ともに様々なアレンジが加わり、もとの大津絵節からはかけ離れてしまったものも多いようです。
現在でも、「京都大津絵節」や「会津大津絵節」など多くが歌い継がれていますが、下にあるのが元祖「大津絵節」です。
げほうの 梯子剃り
雷太鼓で 釣瓶とる
お若衆は 鷹を持つ
塗笠お女郎がかたげた藤の花
座頭のふんどしを犬ワンワンつきや
びっくり仰天し 腹立ち杖をばふり上げる
荒気の鬼もほっきして 鉦しもく
瓢箪なまずを しっかとおさえます
奴さんの尻ふり行列
向ふ八巻釣鐘弁慶
矢の根男子

